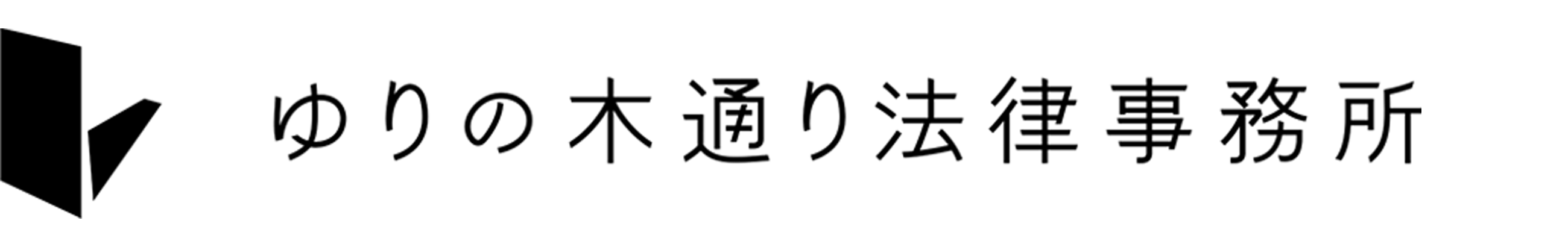法定離婚事由について(民法770条1項4号の改正)
民法第770条は、裁判上の離婚事由を定めています。これまで、第1項第4号では「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が離婚の理由として挙げられていました。しかし、近年の法改正により、この規定が削除されることになりました。本コラムでは、その背景や影響について、弁護士が分かりやすく解説いたします。
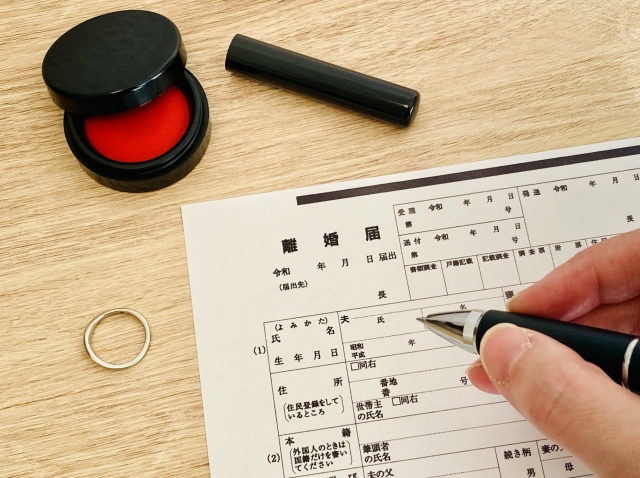
これまでの規定とその問題点
従来、民法第770条第1項第4号では、配偶者が重度の精神疾患に罹患し、その回復が見込めない場合には、離婚を請求できると定められていました。この規定は、長年にわたり、配偶者の看病や支援を行うことが困難であるケースに対応する目的で設けられていました。
しかし、この条文にはいくつかの問題が指摘されていました。第一に、人権侵害の懸念です。精神疾患を理由に離婚が認められるという考え方は、病気を抱える人の尊厳や人格を否定するものとも受け取られかねません。精神疾患を持つ配偶者が、自らの意思とは無関係に離婚されるリスクがある点が批判されていました。
第二に、医学的な観点からの変化も挙げられます。現代の精神医療は日進月歩であり、うつ病や統合失調症など、従来は「不治」と考えられていた疾患も、適切な治療や支援により回復が見込まれるケースが増えています。「回復の見込みがない」と法的に断定することの難しさが指摘されるようになったのです。
第三に、差別の助長という側面です。この規定が存在することで、「精神疾患=離婚理由になり得る」という社会的認識が生まれ、当事者に対する偏見やスティグマを助長するおそれがありました。
民法770条(裁判上の離婚)1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
何がどう変わるのか
こうした問題意識を受け、令和6年の法改正により、民法第770条第1項第4号は正式に削除されるに至りました。これにより、配偶者が精神疾患に罹患しているという事実だけでは、離婚を請求することはできなくなりました。
ただし、離婚がまったく認められなくなったわけではありません。民法第770条第1項第5号には、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という規定があり、精神疾患に起因する事実(たとえば家庭内での暴力、長期間の別居、介護の放棄など)がこれに該当する場合には、引き続き裁判上の離婚が認められる可能性はあります。
改正の本質は、単に「病気であること」そのものではなく、その病状によって婚姻関係が破綻しているかどうかという点に判断の軸を移したことにあります。このような法の見直しは、障害者の権利保護の観点からも大きな意味を持ちます。
法改正の背景
この改正は、家族法制全体の見直しの一環として行われたものです。法務省が公表している「家族法制の見直しに関する中間試案」(令和4年)や、法制審議会家族法制部会での議論では、精神疾患に限らず、「離婚原因の見直し」「婚姻関係の実質を重視する制度改革」などがテーマとして取り上げられてきました。
また、国連の障害者権利条約や、障害者の差別解消に関する国内外の議論を踏まえ、日本の民法における障害者への配慮を強化する必要性が指摘されていました。このような国際的動向と国内の権利保護の意識の高まりが、今回の改正を後押ししたと言えます。
法改正の影響
今回の改正により、精神疾患を理由として離婚が一律に認められる規定は削除されましたが、実務上の影響は比較的限定的といえます。なぜなら、従来から包括的な離婚事由として「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法第770条第1項第5号)が存在しており、精神疾患によって実質的に婚姻関係が破綻していると認められる場合には、引き続き離婚が認められる余地があるからです。
このため、今回の改正は、離婚制度の運用に抜本的な変更を加えるというよりも、「精神疾患そのものを離婚理由とする」という旧来の価値観からの脱却を象徴する法的メッセージと捉えることができます。精神疾患を有する配偶者が、ただその病状の存在のみを理由に離婚されることがなくなった点で、人権保護の観点から重要な意義があります。
一方で、精神疾患により夫婦の協力関係が実質的に失われた場合、例えば家庭内での暴力、長期間の別居、意思疎通の著しい困難といった事情が認められれば、従来どおり裁判所は個別具体的に判断し、離婚を認容することが可能です。その意味では、精神疾患をめぐる離婚の現場においては、適切な証拠と主張を通じた法的な対応が引き続き求められます。
このように、改正の影響は制度的には限定的でありつつも、精神疾患を取り巻く社会的な偏見や差別の是正に向けた一歩として評価されています。今後は、法制度とともに、精神疾患に対する社会的理解や家族支援体制のさらなる充実が期待されます。
諸外国の事例との比較
精神疾患と離婚事由に関する規定は、国によって大きく異なります。例えばアメリカでは、州ごとに離婚制度が異なりますが、多くの州で"no-fault divorce"(過失なし離婚)が導入されており、精神疾患の有無に関わらず「婚姻関係の破綻」をもって離婚が認められるケースが一般的です。
イギリスでは、2020年に離婚法の大改正が行われ、2022年4月6日に「離婚・解消および司法分離に関する法律(Divorce, Dissolution and Separation Act 2020)」が施行されました。この法律により、いわゆる"no-fault divorce"が導入され、夫婦のいずれか一方が「婚姻が取り返しのつかないほど破綻した」と申し立てるだけで、離婚の申立てが可能となりました。これにより、配偶者の同意がなくても離婚申立てができるようになり、従来のような責任追及(不貞行為、暴力など)の主張や証明が不要となりました。この制度改革は、離婚の過程を対立的なものから協調的なものへと転換させる目的があり、精神疾患を理由とした離婚についても、当事者間の合意や対話に基づいた判断が重視される方向に進んでいます。
ドイツやフランスでも、精神疾患を特別な離婚事由とする明文規定はなく、婚姻生活の継続困難性を総合的に判断する方式がとられています。これらの国々においても、精神疾患そのものではなく、婚姻関係にどのような影響が生じているかを重視する点は共通しています。
離婚手続きに関する最近の変更点
なお、離婚手続きそのものに関しても、近年いくつかの実務的な変更が行われています。たとえば、2021年9月1日より、協議離婚における『離婚届』への押印(署名欄の印鑑)は任意となり、押印がなくても離婚届は有効とされるようになりました(法務省:戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行について:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html)。
また、2024年3月1日施行の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村役場へ離婚届を提出する際、これまで必要だった戸籍謄本の添付が不要となる制度が開始されました(法務省:戸籍情報連携に関するお知らせ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)。マイナンバーカードや住民票コードなどを利用することで、届出先の役所が戸籍情報をオンラインで確認できるようになったためです。
これらの改正により、離婚手続きの利便性が向上し、よりスムーズな届け出が可能になっています。
まとめ
民法第770条第1項第4号の削除は、精神疾患を理由とした離婚に関する法制度の大きな転換点です。この改正により、病気や障害を持つ人々の権利がより尊重される社会への第一歩が踏み出されました。
今後も、精神疾患を抱える家庭に対する福祉的支援や、配偶者間のトラブルを円滑に解決する法制度の整備が期待されます。離婚制度は、家族の在り方そのものを映す鏡です。私たち一人ひとりが、法制度と現実の間にある課題を見つめ直し、より公正で包摂的な社会を築いていくことが求められています。
最後に、当事務所の紹介を少し。ゆりの木通り法律事務所は、浜松市中央区にある小さな法律事務所です。離婚についてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。