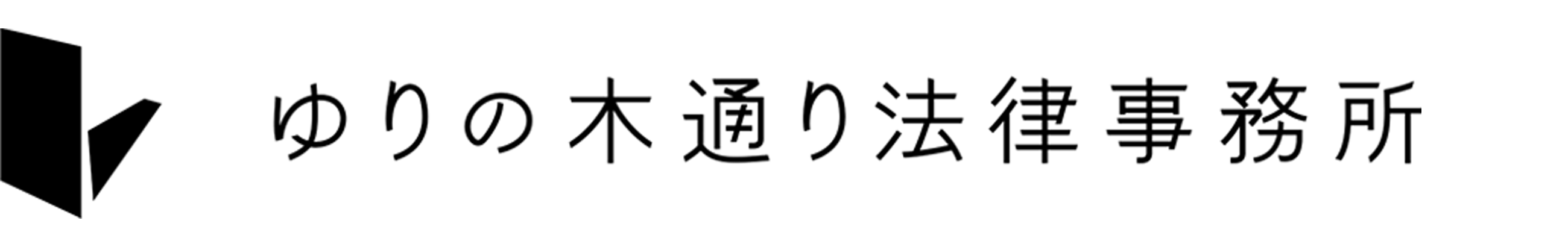破産という選択肢を前向きにとらえるために――法人の破産申立ての意義と概要
「破産」は本当に“最後の手段”なのか?
先日、2024年に倒産した企業(負債総額1千万円以上)が11年ぶりに1万件を上回った(東京商工リサーチ発表)とのニュースを耳にしました。私の実感としても、浜松市やその周辺地域における企業の経営者の方から、債務に関する相談が増加しているなと感じていたところです。
私は、日頃、中小企業の経営者の方とお話しするなかで、これまで何度となく「破産だけは避けたい」という強いお気持ちを伺う機会があります。経営者として事業の成長に人生を捧げてきたのですから、そのお気持ちは当然のことです。破産という言葉には、どうしても「終わり」や「失敗」といったネガティブなイメージがつきまといます。
しかし、いつも私がお話しするのは、破産とは、決して経営者の人格を否定するものではありません。ましてや、経営努力が足りなかったという烙印を押すものでもありません。破産とは、法律が定めた正当な「整理のための手続き」であり、適切な時期に申し立てることで、経営者個人や関係者の二次被害を防ぎ、次の一歩を踏み出すための再出発を可能にする制度です。
今回は、あえてこの「法人の破産申立て」というテーマについて、正面から向き合ってみたいと思います。特に、中小企業を経営されている方々に向けて、破産を前向きな選択肢として捉えるための視点をお届けいたします。

法人破産手続の基本的なしくみ
まず、一般論として、「破産」とは、支払不能に陥った債務者(個人も法人も含まれます)の財産を裁判所(管財人)の管理下に置き、債権者に対して公平に配当する手続です。その後、残った債務については、支払義務を免除(免責)します。法人破産の場合、破産手続開始決定と同時に会社は清算に向かうため、存在自体がなくなります。破産手続の概略については、裁判所のウェブサイトもご参照ください。
破産法において、破産手続開始の原因となるのは「支払不能」、すなわち、会社がその債務を一般的・継続的に支払うことができない状態です。これが認められれば、代表者等からの申立てに基づいて裁判所は破産手続を開始します。申し立ての時点で債務超過になっており、収入の目処もないのであれば、「支払不能」の認定はそれほど厳しくありません。
なお、静岡地方裁判所では、法人が破産を申し立てる場合、代表者個人も同時に破産を申し立てることが原則とされています。法人の借入に対して代表者が個人保証をしていることがほとんどであるため、代表者の経済的な再生のため、代表者個人の破産手続も同時に進めることが必要となるのです。
破産申立てのメリット
1.差押えや督促から解放される
破産手続が開始されると、債権者による個別の差押えや督促行為はすべて法律により禁止されます。これにより、取引先や金融機関からの厳しい取り立てに日々追われる状況から脱することができ、精神的にも安定した状態で冷静に今後の対応を検討することが可能になります。代表者や場合によっては従業員にとっても、生活や業務が混乱から解放される重要な効果があります。
2.代表者個人の再出発の道が拓ける
上記のとおり、法人の借入に代表者が個人保証をしている場合が多いため、代表者が法人とともに個人破産を申し立てることで、債務から解放され、生活の立て直しが可能になります。破産手続を通じて法的に整理を行えば、無秩序な返済を続けるよりも早期に再出発が図れる可能性が高まります。静岡地裁の運用を踏まえ、法人と個人を一体として整理する視点が重要です。
3.関係者の損害を最小限に抑える
経営を続けながら債務を膨らませてしまえば、従業員の未払給与や取引先への代金未払といった影響が連鎖的に拡大し、関係者に深刻な損害を与えるおそれがあります。経営改善の見込みのない事業に代表者が個人資産をすべてつぎ込み、それでも足りなくて親族などから借金を繰り返すような事例を沢山見てきました。早期に破産を申し立てることで、法的枠組みのもとで被害の範囲を限定し、秩序ある清算が可能になります。これは経営者としての責任の果たし方でもあります。
4.従業員とその家族の生活を守る
給与の遅配や解雇の混乱が起きる前に、計画的に破産手続を行えば、従業員に対して説明や対応の時間が確保され、混乱を回避できます。労働者健康安全機構の立替払制度なども活用できるため、未払給与等を一定程度確保することができ、従業員とその家族の生活基盤を守る結果にもつながります。破産は、あなたの大切な従業員の生活を「守るための手段」としても重要です。
5.反社会的勢力の介入を未然に防ぐ
資金繰りに窮した企業が、やむなく非合法な資金提供者やいわゆる「事件屋」に頼ってしまう事例も現実にあります。資金繰りに窮した状態は人の思考力を奪い、視野を狭め、普段は歯牙にもかけないような特殊詐欺の手口に騙されたという事例も少なくありません。法律に則って破産の申立てをすることで、裁判所と破産管財人の管理下における透明な手続が始まり、こうした不当な介入の余地を排除できます。法的手続こそが、企業と経営者を不正な圧力から守る最善の方法となります。
法人破産の大まかな流れ
破産申立てから終了までの大まかな流れは次の1から5のとおりです。法人の破産申立ては、原則として主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所にする必要があります。日本各地にある裁判所は、それぞれ独自の破産手続のルールを持っておりますので、以下の流れはあくまで参考程度の一般的なものとご理解ください。それぞれの地域のルールは、その地域の弁護士にご相談いただくのが一番早いと思います。
- 【事前相談・資料収集】 財務諸表、資産・負債一覧、取引先リスト、従業員名簿などの資料を弁護士と共に準備します。
- 【裁判所への申立て】 管轄裁判所に破産申立書を提出し、代表者個人の申立ても併せて行います。
- 【破産手続開始決定・破産管財人の選任】 裁判所が開始決定を出し、破産管財人が選任され、資産調査・換価が始まります。
- 【財産の換価・債権者対応】 管財人が会社の財産を売却し、債権者に配当する準備をします。
- 【債権者集会・手続終了】 手続の報告と配当後、手続が終結します。
費用の目安
法人破産の費用は、会社の規模や資産の有無により異なりますが、一般的な中小企業の場合は以下が目安です。
- 裁判所への予納金:だいたい100万円~(業務量や債務の金額によって変動します)
- 弁護士費用:だいたい100万~(業務量や債務の金額によって変動します)
法人の破産にはそれなりの費用が必要になります。そのため、本当にギリギリの状態になってからでは、破産すら満足にできないのです。従業員の給与が未払いのまま解雇を告げるような事態を想像してみてください。そのような事態を避けるためにも、早めの相談と準備が必要です。
なお、資産が乏しい場合でも、場合によっては法人名義の資産売却や債権の回収などによって費用を捻出する工夫ができることがあります。
相談できる弁護士との関係づくりを
以上のとおり、破産は決して「逃げ」でも「失敗」でもなく、適切に活用すればご自身の「再起」と関係者への「配慮」の手続になります。資金繰りに行き詰まったときには、破産も選択肢の一つとして冷静に検討すべきです。実際に申立てをするかどうかは別として、まずは一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
そして、日ごろから気軽に相談できる弁護士との関係を作っておくことが何よりの備えになります。事態が深刻化する前に「気軽に相談できる専門家」がいることが、経営者にとって大きな支えとなるのです。
浜松市など静岡県西部地域の方は、破産に限らず、事業上のトラブルや法的な選択肢について悩まれた際には、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。ゆりの木通り法律事務所は、債務に関するご相談は初回相談料無料で承ります。お問い合わせは当事務所メールフォーム又は電話にてどうぞ。