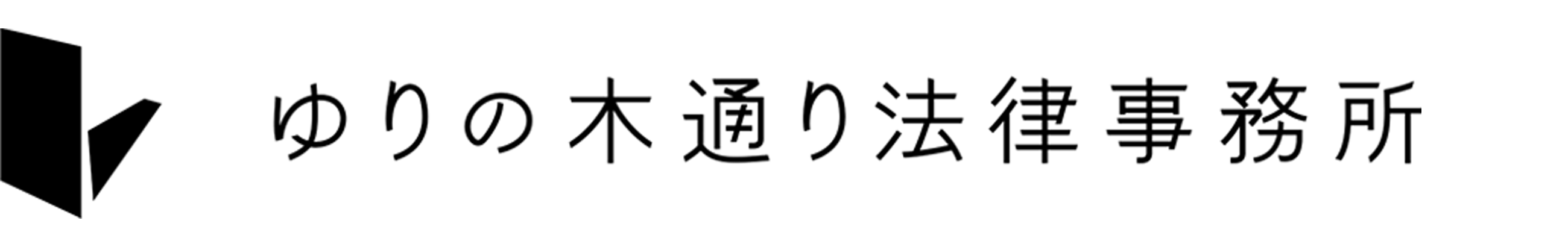判例紹介:成人に達した子から父に対する扶養料の請求が認められた事例(福岡高決令和元年9月2日家庭の法と裁判39号54頁)
事案の概要
BとCが婚姻し、平成4年に子Aを、平成7年に子Dを設けた。その後、BとCは、平成20年に離婚した。その際、子らの親権者をCとすること、Aの養育費として平成20年9月から平成26年3月まで月額6万円を支払うこと、Dの養育費として平成20年9月から平成26年3月まで月額6万円、平成26年4月から平成30年3月まで月額8万円を支払うこと、子らの養育費は物価変動などの事情に応じてBとCの協議によって増減できることなどを合意し、公営証書を作成した。
Aは、平成26年4月以降、大学生として精神疾患を治療しながら平成31年3月の卒業を目指して通学する予定であるものの、薬の副作用などで当面の間就労できる見込みがなく、その間の生活費の他、大学の授業料、通学日、治療費等の費用を要する要扶養状態にあり、他方でBはAの父として扶養能力があるとして、Bに対してAが就労するまでの附票量を支払うべきと主張した。
これに対し、原審(福岡家庭裁判所小倉支部)は、離婚後の紛争調整調停により扶養料請求権が清算済みであること、Aが大学に関する費用を賄えないことをもって要扶養状態にあるとは認められず、自らの心身の状態に即した経済的自立を図るべきであり、精神疾患によって稼働能力が制限されているといっても稼働能力が全くないとはいえないこと、Cと同居して生活費は相当に抑えられていること、他方でBはこれまで子らへの養育費を支払い、自らの家庭の生活費や通院費などで経済的な余力があるとはいえないとして、Aの請求を却下した。かかる原審の決定に対してAが抗告。抗告審(福岡高等裁判所)は、原審の決定を取消して、下記のとおり扶養料の支払いを命じた。
本決定の内容
Bは、公正証書において、Bの扶養義務の終期をAが満22歳に達した後の最初の3月である平成26年3月までとする合意をしている。そうだとすれば、Bは、Aの大学在学中、C(離婚した元妻)とともにAの扶養義務を負うことを了承しているといえる。その後、Aは精神疾患によって大学卒業が大幅に遅れたが、そのことについてAに責任があるということはできず、Aが自らの経済的な自立のために大学進学する必要が乏しかったともいえない。したがって、Bは、Aが大学を卒業した平成31年3月までの間、CとともにAの扶養義務を負うというべきである。
本件において、BとCが分担するAの扶養義務は、未成熟子に対する生活保持義務であると解するのが相当であるから、その分担額は養育費の標準算定方式に基づいて算定されるべきである。そのため、Bは、Aに対し、平成26年4月から平成30年3月まで月額3万5000円、同年4月から平成31年3月まで月額10万円の養育費を支払うべきである。
解説
未成年の子に対する親の扶養義務は、民法766条1項を根拠に、自己と同程度の生活を保障する「生活保持義務」と解されている。他方で、成人した子に対する親の扶養義務は、原則として、民法877条1項を根拠とする余力の範囲で援助を行う「生活扶助義務」と解され、両者は区別されている。
本件は、成人した子からの扶養請求であるため、原則通りであれば、後者の「生活扶助義務」となる。しかし、成年に達した子であっても、大学教育の一般化、子の適性や脳旅行、親の学歴や職業、資力などを考慮して、未成熟子(事故の資産又は労力で生活できる能力がない者)として婚姻費用又は養育費の支払いを命じる事例が見られる。現在の家庭裁判所の実務としては、請求時に子が成年年齢に達していたとしても、監護親は子が未成熟子である以上、民法766条1項の適用又は類推適用によって、成年年齢に達した子の監護費用を養育費等として請求できるという運用をしている(司法研修所編『養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』法曹会、2019、p.59)。
本件決定は、家庭裁判所の運用に従い、大学進学の了解の有無、支払義務者の地位や学歴や収入などを考慮し、父親であるAに大学卒業時までの養育費相当額の扶養料の支払いを命じたものである。
精神疾患やその他の事情によって子に就労能力がなく、成人に達した子の養育費を請求したいという要望は多いものと考えられるところ、本件決定は実務において参考になるものといえる。
民法766条1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
民法877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
判例抜粋
相手方(B、Aの父親)は、平成20年8月に母と離婚するに際し、本件公正証書において、相手方の養育費支払義務の終期を、抗告人(A、Bの子)が満22歳に達した後の最初の3月である平成26年3月までとする旨合意しているところ、抗告人が当時高校2年生であったことなどに照らせば、相手方は、抗告人の大学在学中、母とともに、抗告人の扶養義務を負うことを了承したものというべきである。
その後、抗告人は、精神疾患を発症し、入通院等により、本件公正証書が作成された当時の想定よりも大学卒業が大幅に遅れたものであるが、そのことについて抗告人に責任があるということはできず、また、抗告人が自らの経済的自立のため大学に通学する必要性に乏しかったということもできない。したがって、相手方は、本件公正証書に基づく養育費支払義務の終期の翌月である平成26年4月から、抗告人が大学を卒業した平成31年3月までの間、母とともに、抗告人の扶養義務を負うというべきである。
これに対し、相手方は、前件清算条項において、相手方が母に対し本件公正証書に定められた限度を超えて子らの養育費を支払う義務を負わないことが確認されたのであるから、抗告人は平成26年4月以降の扶養料分担義務を負わない旨主張する。しかしながら、抗告人の相手方に対する扶養請求権は、母が放棄することができないものであり、前件清算条項は抗告人の扶養請求権の帰趨に何ら影響を及ぼすものではないというべきである。相手方の上記主張は、採用することができない。
なお、抗告人は、平成26年4月以降、平成29年12月22日の本件申立てに至るまで、相手方に対し、扶養料の支払を求めることがなかったところ、相手方は、平成26年4月以降の扶養料を抗告人から請求されないという相手方の期待は保護されるべきであるなどとして、抗告人の扶養料請求が過去に遡って認められるべきではない旨主張する。しかしながら、本件記録によれば、相手方は、抗告人が平成26年3月に至っても大学を卒業できておらず、要扶養状態にあることを知りながら、同年4月頃以降、抗告人との連絡を絶ち、平成28年7月に入院中の抗告人が相手方の勤務先に電話連絡したところ、相手方は抗告人の入院先に電話し、抗告人の主治医に対し、抗告人と直接会うことや話をすることは難しい旨告げ、抗告人との関わりを拒絶していたことが認められる。そうすると、抗告人が相手方に対し扶養料の支払を求めなかった主たる原因は、抗告人の健康状態に加え、上記のような相手方の対応にあったといえるのであるから、平成26年4月以降の扶養料を抗告人から請求されないという相手方の期待が保護に値するものであるとはいえない。また、本件記録を精査しても、平成26年4月から平成29年12月22日までの間、母のみが抗告人の扶養義務を分担すべき事情は認められず、むしろ、本件記録から認められる離婚後の事情や相手方及び母の収入及び資産の状況に照らせば、相手方が平成26年4月以降の抗告人の扶養料の分担義務を免れることは著しく公平を害するものといえる。したがって、相手方の扶養料分担義務の始期を平成26年4月より後らせるべきではなく、これに反する相手方の主張は、採用することができない。
他方、抗告人は、大学卒業後も抗告人の就労の目途は立っていないのであるから、抗告人が就労するまでの間、相手方の扶養義務が認められるべきである旨主張する。しかしながら、抗告人が大学を卒業後にいかなる職に就くかは、抗告人が自らの判断により決すべき事柄であり、抗告人が未だ就労に至っていないからといって、稼働能力を有しないということはできない。したがって、抗告人の上記主張は、採用することができない。
*括弧内は筆者註