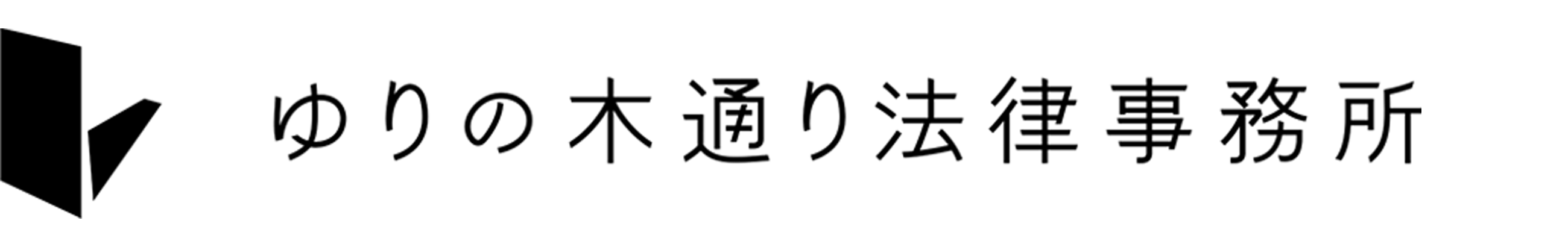意思能力に関する法律問題
意思能力とは何か?
近代民法は,個人が自由な意思に基づき自らの私的生活関係について決定することができ,国家は個人が下した決定を尊重するという「私的自治の原則」を基本原理のひとつとして捉えています。そして,私的自治の原則の論理的前提となる権利主体の自己決定能力のことを「意思能力」といいます(潮見佳男『民法総則講義』2005有斐閣p.108)。簡単にいえば,意思能力とは,法律上の判断ができる能力のことです(川井健『民法概論1民法総則[第3版]』2007有斐閣p.21)。
意思能力のない者が行った法律行為は,その当然の帰結として,「無効」とされてきました(大判明治38年5月11日民録11輯706頁)。これまで,民法にはこのような意思能力に関する規定はありませんでしたが,平成29年法律44号による民法の改正によって,「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは,その法律行為は,無効とする。」との条文が3条の2に追加されました。
民法改正の担当者によれば,高齢化社会の進展に伴い,判断能力が減退した高齢者をめぐる財産取引上のトラブルが増加したことを受け,意思能力に関して明文で規定するべきだと考えたようです(潮見佳男『Before/After民法改正』2017弘文堂p.3)。
意思能力の基準は?
意思能力として要求される能力は,個々の行為者ごとに個別的に判断されます。一応の目安としては,小学校入学ないしは小学校低学年の知能程度が挙げられていますが(潮見・前掲書p.109),画一的な解釈は存在しません。
これまで意思能力が問題となった裁判例では,法律行為の性質,行為者の見当識障害や短期記憶障害の程度,行為者が当該法律行為を行う客観的必要性や合理性などを総合的に考慮して,個々の事案ごとに意思能力の有無を判断しています。判断基準時は,法律行為の時点です。
なお,裁判例では,見当識障害や短期記憶障害の程度を判断するために,長谷川式知能評価スケール(HDS-R)やミニメンタルステート検査(MMSE)の評点が利用されています。
長谷川式知能評価スケールは,認知症医療の第一人者である長谷川和夫博士が作成した簡易的な知能テストです。質問者が被験者に対して自己の見当識や時間に関する見当識などを問う9つの質問を行い,30点満点で評点を算出します。そして,評点が20点以下の場合には,認知症である可能性が高いとされています。
他方で,ミニメンタルステート検査は,アメリカで開発された認知症の診断用の知能テストです。見当識,記憶力,計算力などを問う11の質問からなり,30点満点で評点を算出します。10点未満で高度な知能低下,20点未満で中等度の知能低下,24点以上が正常とされています。
これらの知能テストの評点は,上記のとおり,意思能力を判断するための一つの基準にはなりますが,絶対的なものではありません。意思能力は法律概念であり,医学的な検査の結果を機械的に当てはめることはできないからです。知能テストの評点が同じであっても,法律行為の内容次第で意思能力が認められる場合もあれば認められない場合もあります。
行為能力とは?
上記のとおり,意思能力のない者による法律行為は無効とされます。しかし,意思能力がない者が事後的にそれを証明して法律行為を無効にすることは大変に手間がかかりますし,取引の相手方にも不測の損害をもたらすことになります。
そのため,民法では,判断能力の低い者について,画一的に「行為制限能力者」として扱い,これを公示して保護することにより,併せてその取引の相手方を保護するという制度を設けています。民法が定める行為制限能力者は,①未成年者,②成年被後見人,③被保佐人,④被保佐人の4者です。行為制限能力者が行った行為は,意思能力を有しない場合の無効とは異なり,事後的に取り消すことができます。
なお,婚姻や養子縁組などの身分行為については,本人の意思を尊重する必要があるため,能力の制限に関する民法の規程は原則として適用されません。また,民法962条が「第5条(未成年者の法律行為),第9条(成年被後見人の法律行為),第13条(保佐人の同意を要する行為等)及び第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)の規定は,遺言については,適用しない。(括弧内筆者注)」と規定しているため,遺言についても対象外となります。
ただし,「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(民法7条)とされる成年被後見人は,症状の回復がない限り(民法973条),一般的には遺言能力がないものと考えられています。さらに,多くの裁判例では,遺言能力と意思能力は等しいものとして理解されています(例えば,東京高判平成25年3月6日判タ1395号256頁)。
意思能力が問題となった事例①
28歳の知的障害者である本人が知人の150万円の債務について連帯保証契約を締結したことを受け,本人の叔母が保佐人となって連帯保証契約は意思無能力によって無効であると争った事案(福岡高判平成16年7月21日判タ1166号185頁)において,裁判所は,「意思能力とは,自分の行為の結果を正しく認識し,これに基づいて正しく意思決定する精神能力をいうと解すべきである」とした上,①本人の金銭の価値についての理解は数百万円以上について及んでいないこと,②本人が連帯保証契約において定められた利息や遅延損害金の意味を理解できていないこと,③本人は他人から強く指示されると抵抗できない性格であることなどから,「本人は本件連帯保証契約締結の結果を正しく認識し,これに基づいて正しく意思決定を行う精神能力を有していなかったというべきである」と判断した。
なお,裁判所は,本件連帯保証契約後に本人について保佐開始の審判(後見開始の審判ではなく)がなされていることについて,「意思無能力かどうかは,問題となる個々の法律行為ごとにその難易,重大性なども考慮して,行為の結果を正しく認識できていたかどうかということを中心に判断されるべきものであるから,本人について一般的に事理弁識能力が著しく不十分であるとして,平成15年9月17日保佐開始審判がなされたことは,本件連帯保証契約について意思無能力の判断をする妨げとなるものではない」と述べている。
意思能力が問題となった事例②
本人が多数の不動産を推定相続人の一人に負担付死因贈与(公正証書による契約書作成)をしたところ,本人の死後他の相続人から意思無能力を理由として同契約の無効確認を求める訴えがなされた事案(東京地判平成22年7月13日判時2103号50頁)において,裁判所は,①病院入院後,本人には通常人には見られないような言動があったことが認められ,診療情報提供書にも「認知症」との記載が存在するが,入院中毎日問診をしていた医師によれば,医師が話しかければ大体は何かしらの返答が来るが,病気が悪化しているときは意識がもうろうとして返答がないこともあったとか,相手の話を理解して会話が成り立つときもあれば,相手の話を理解することができないときもあるという波のある状態であったと供述しており,この供述を前提とすれば,医師は本人を認知症と判断していたものの,これをもって太郎が常に意思能力のない状態であったとは認められない,②本人は,病院入院時には要介護度1と判定され,その後要介護度2に変更されたが,要介護度は認知の能力のみならず身体能力も併せて判断することから,要介護度1や2と認定された者が常に意思能力を欠く状態にあるとは認められない,③公証人が,公正証書作成に際して本人の意思能力に問題がないことを確認した上で作成にとりかかったこと,④被告(受贈者)が本人の入院のための手続及びその医療費の支払行為を行ったこと等からすれば,少なくとも本人が病院に入院した以降,被告と本人が絶縁状態であったとは認められず,太郎が被告に対して財産を贈与する動機がなかったとまでは認められないなどとして,意思無能力であったという原告の主張を退け,「本件贈与契約はいずれも有効に成立した」ものと判断している。
高齢者との間で契約を結ぶ場合に注意することは?
高齢者との間で何らかの契約を締結する際には,上記のとおり,事後的に意思能力を争われる可能性を可能な限り排除すべきです。例えば,医師による長谷川式知能評価スケールやミニメンタルステート検査を受けておく,契約書は公証人に依頼して公正証書で作成しておく,契約に至った過程を動画などで記録に残しておくなどの方法が考えられます。
契約にあたり,ご本人の意思能力について不安がある場合には,弁護士にご相談いただくのもよいでしょう。当事務所にご相談いただければ,個別的な事情に応じて,紛争のリスクを軽減する方法をご提案いたします。